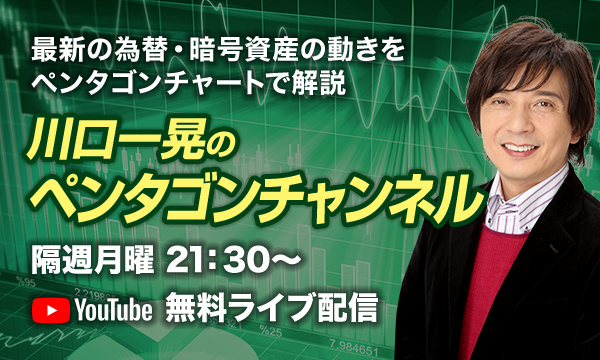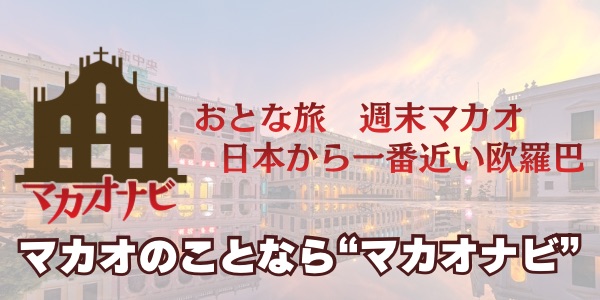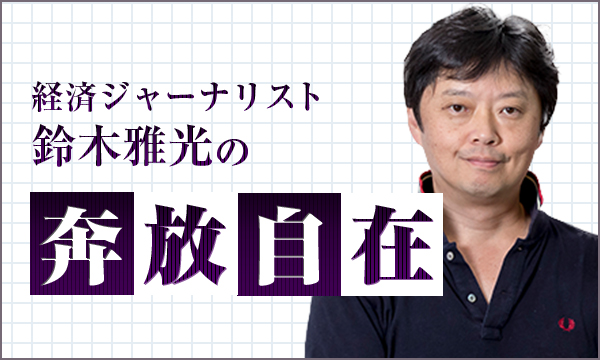債券投資の基本
> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!

17年ぶりに長期金利が1.595%まで上昇!債券価格との関係や、投資信託・住宅ローンへの影響など、「債券投資の基本」を解説します。
日本の長期金利が上昇しています。7月15日の長期金利は一時1.595%まで上昇しました。これは約17年ぶりの水準です。
長期金利とは、日本の場合、10年国債の利回りを意味しています。10年国債とは、発行してから償還までの期間が10年の、国が発行する債務証書のことです。これを「長期国債」と称することもあります。
長期国債は額面価格100円に対して、年1%、2%というように利子が付きます。このように額面金額に対して一定率の利子が定期的に支払われる債券を「利付債」と言います。つまり日本の長期国債は、10年物利付国債ということになります。
さて、長期国債は発行された後、債券市場で自由に売買されます。市場で売買されるためには、いくらで売買するのかという「価格」が必要になります。つまり「償還までの期間が10年で、額面金額100円に対して年1%の利子が得られる国債をいくらで売買しますか?」ということです。この債券市場で売買される際の価格が「債券価格」です。

つまり債券は、償還する際には額面金額で償還金を受け取ることになりますが、償還日前に債券市場で売買する場合には、売り手と買い手の力関係によって形成される債券価格で取引されるのです。
債券価格は買い手が多いほど値上がりし、売り手が多いほど値下がりします。たとえば毎年1%の利子が得られる長期国債に投資妙味があると思う投資家が多ければ買いが増えて、額面金額100円に対して債券価格が100円50銭、101円というように値上がりしていきます。
たとえば額面100円に対して債券価格が101円になったとします。すでに発行から5年が経過しているこの長期国債を償還まで保有するとしたら、残り5年間で得られる利子の総額は、額面100円に対して5円です。これを年利回りに換算すると1%、と言いたいところですが、投資家はこの長期国債を101円で購入しています。そして長期国債が償還される時は、額面金額である100円で戻ってくるため、1円の償還差損を抱えることになります。この償還差損分を含めて、トータルで収益率が何%になるのかを計算すると、利回りは0.792%になります。
一方、毎年1%の利子が得られる長期国債には投資妙味がないと思う投資家が多くて売りが増え、額面100円に対して債券価格が99円になったとします。償還までの期間は5年で、残り5年間で得られる利子の総額は、額面100円に対して5円。この債券を99円で買って償還まで保有すると、1円の償還差益が得られます。この償還差益分を含めて、トータルで収益率が何%になるのかを計算すると、利回りは1.212%になります。
以上が債券の基本的なメカニズムになります。つまり利回りが上昇すると債券価格は下落し、利回りが低下すると債券価格は値上がりするのです。
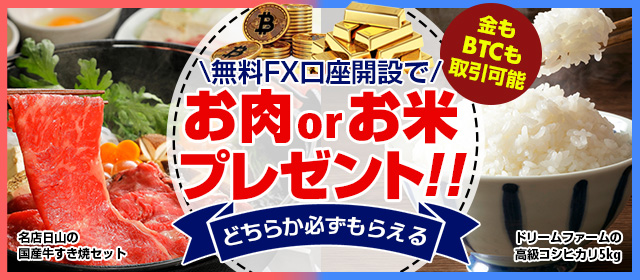
ここで冒頭に戻ると、7月15日の長期金利が一時、約17年ぶりに1.595%まで上昇したとのことですが、このように長期国債の利回りが上昇したということは、長期国債が債券市場で売られていることを意味します。つまり日本国債を持つのはリスキーだ、あるいは日本国債を保有する魅力が低下していると、債券市場の売買に参加している大勢の投資家は考えているのです。
では、どうして日本国債の魅力が低下したと考えられているのでしょうか。
目先の材料としては、20日に開票される参院選挙の結果を見越してのものです。すでにニュースなどでも報じられている通り、参院選挙で与党が過半数割れを喫すると、政府が作成する法案が議会を通りにくくなります。当然、政策によっては一部の野党と手を組みながら法案を通さなければならなくなりますが、その際に多くの野党が選挙公約的に打ち出している消費税率の引き下げを、与党が呑まざるを得なくなる状況も想定されます。
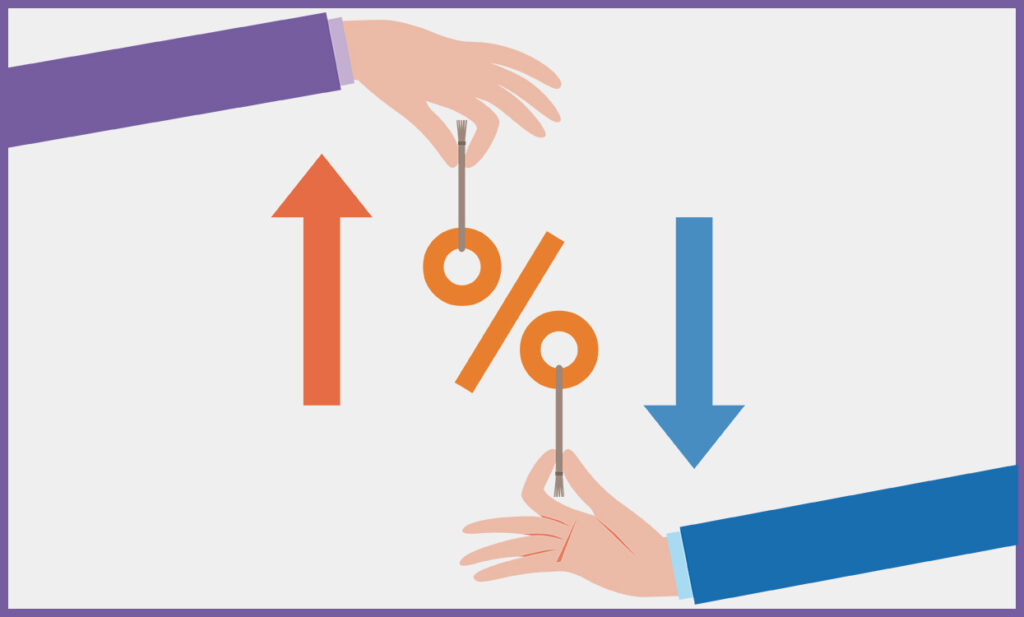
しかし、消費税率を下げれば税収減になり、最終的に政府は長期国債を発行せざるを得なくなります。長期国債の発行が増えれば増えるほど、債券市場における長期国債の需給関係は悪化する恐れが高まるため、長期国債が売られて長期金利が上昇している、というわけです。
こうした長期金利の上昇は、たとえば投資信託などで長期国債を多く組み入れて運用しているファンドの運用成績にも悪影響を及ぼします。「長期金利の上昇=債券価格の下落」であり、ファンドに組み入れられている長期国債の評価損が増えるからです。これが基準価額の下落につながります。
また長期金利が上昇すれば、銀行の優良企業向け融資の金利である長期プライムレートの上昇につながります。それは個人が銀行から固定金利型の住宅ローンを借り入れる際の適用金利にも影響を及ぼします。
実際問題、この長期金利の上昇がさらに進むのかどうかは、何とも言えませんが、仮にもう一段の上昇となれば、運用商品の成績悪化だけでなく、企業の設備投資や個人消費にもネガティブな影響を及ぼしかねません。ここしばらく、長期金利がどこまで上昇するのかには、要注目です。
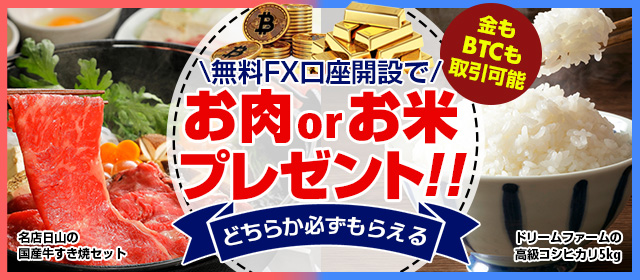

鈴木雅光(すずき・まさみつ)
金融ジャーナリスト
JOYnt代表。岡三証券、公社債新聞社、金融データシステムを経て独立し(有)JOYnt設立し代表に。雑誌への寄稿、単行本執筆のほか、投資信託、経済マーケットを中心に幅広くプロデュース業を展開。
> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!