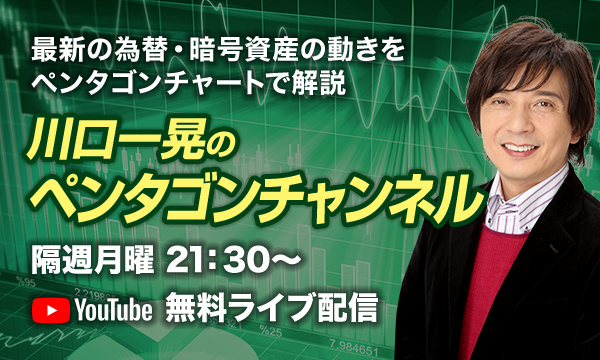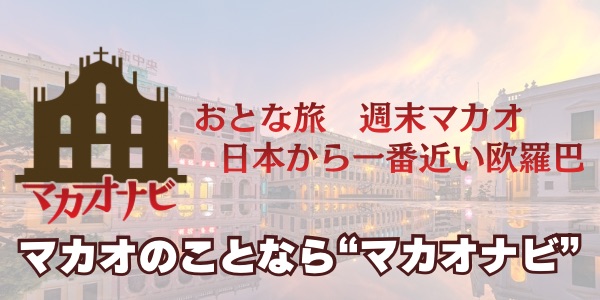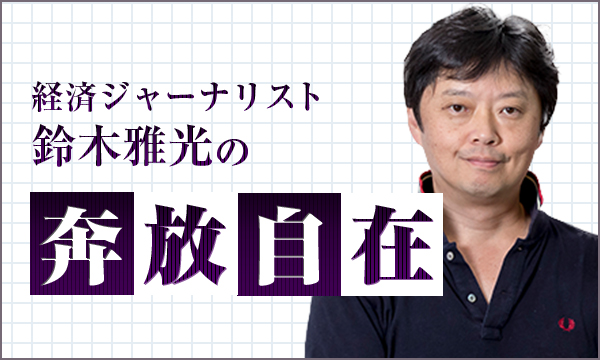再び注目を集め始めた「毎月分配型ファンド」
> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!

NISA制度の浸透とともに、高齢層のニーズに応える「毎月分配型ファンド」に再び注目が集まっています。その仕組みとリスクとは?

NISAについては2024年1月に制度の見直しが行われ、口座数が増加傾向をたどっているのは周知のとおりだ。ちなみに、2025年4月3日に金融庁が公表した資料によると、2024年12月末時点の口座数は2560万4058口座で、制度見直しが行われる直前、2023年12月末の2248万6363口座から見ると、13.86%の増加となっている。
では、2560万4058口座という数字は、何を意味するのか。NISAの口座開設が可能な日本人人口全体における浸透率はどうなのだろうか。これを世代別に見てみたい。世代別の口座数は直近が2024年9月末時点なので、その数字を用いると共に、2024年10月1日時点の人口推計から各世代の人口を割り出し、浸透率を計算すると以下のようになる。
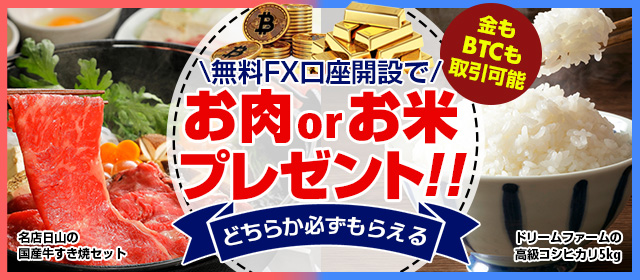
日本人人口全体におけるNISA口座開設浸透率
| 年代 | 浸透率 |
|---|---|
| 10歳代 | 1.21% |
| 20歳代 | 22.53% |
| 30歳代 | 33.10% |
| 40歳代 | 29.48% |
| 50歳代 | 26.32% |
| 60歳代 | 24.88% |
| 70歳代 | 17.77% |
| 80歳代以上 | 11.71% |
30歳代は3人に1人がNISA口座を開設していることになるが、70歳代になるとNISA口座の開設率は大きく低下し、それは80歳代以上も同様だ。
理由は言うまでもなく、NISAが資産形成層にフォーカスした制度設計になっているからだ。しかし高齢者は、今さらS&P500やオール・カントリーなどのインデックスファンドで長期投資をするよりも、定期的に安定したキャッシュフローを得たいというニーズの方が高い。「プラチナNISA」などと称して、NISAでは買えないはずの毎月分配型投資信託を買えるようにする方針を打ち出しているのは、70歳代、80歳代以上の口座開設率を高め、NISAの口座数、口座残高を増やしたいという、政策当局の意向が働いているのかも知れない。
実際、金融資産の多くを保有しているのはこの世代だけに、NISA口座の開設に動けば、口座数、口座残高はもう一段伸びる可能性は高い。
しかし毎月分配型投資信託は、「定期的に安定したキャッシュフローを得る」という高齢者の運用ニーズに合致した商品なのだろうか。
かつて毎月分配型投資信託といえば、国内外の債券を組み入れるタイプが中心だった。しかし近年では、海外株式を主要投資対象としたうえで、毎月分配を行うタイプが人気を集めている。
たとえば外資系運用会社であるインベスコが設定・運用している「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」は、4月28日現在で1兆7862億2200万円もの純資産総額を持っている。
ファンド名にもあるように、このファンドは世界中の厳選された株式でポートフォリオを構築し、毎月決算を行って、前回決算の翌営業日から今決算日までの運用期間中に得られた運用収益を中心にして分配金を支払うという仕組みを持っている。ちなみに毎月の分配金は非常に安定していて、2017年1月から毎月150円以上であり、2020年1月以降は64期にわたって毎月150円をキープしている。
ここで疑問がひとつ出てくる。株式のアクティブ型ファンドである以上、組入銘柄の値動き次第では、決算日時点で損失が生じていることもある。そうであるにも関わらず、なぜ毎回150円という一定額の分配金支払いを、64期にもわたって続けられるのか。
運用報告書には「分配原資の内訳」という項目があるので、それを見ると理由が分かる。
分配金の内訳は「当期の収益」と「当期の収益以外」という2つの項目がある。前者は純粋に運用によって得られた収益で、ファンドに組み入れられている株式の配当金、債券の利金、それぞれのキャピタルゲイン、そして海外資産に投資している場合は為替差益が含まれている。
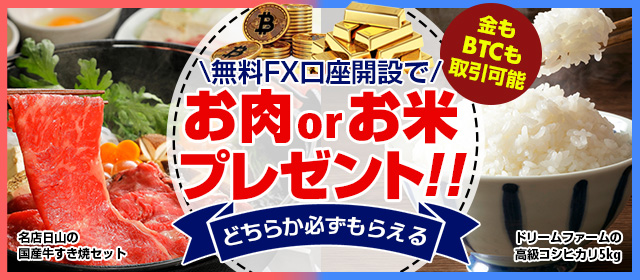

この当期の収益が記載されていない期は、運用収益が得られなかったことを意味する。にも関わらず150円の分配が行われるのは、「当期の収益以外」という勘定から分配金が支払われるからだ。
では、「当期の収益以外」とは何か。
これも2つあって、「分配準備積立金」と「収益調整金」がそれだ。分配準備積立金は、分配されずにファンド内に留保された収益の設定来の累積であり、収益調整金は追加設定時に既存の受益者が本来受け取るべき分配金額が希薄化されてしまうのを防ぐために設けられた勘定である。
これらは現在の基準価額に反映されている、過去からの収益金のことだ。しかし、「当期の収益以外」の部分から分配金の多くが支払われると、ファンドの組入資産が値上がりしたとしても、基準価額には常に下落圧力がかかってしまう。これが「タコ足分配」と言われる所以だ。
すべての毎月分配型投資信託がタコ足分配を行っているかどうか、すべてを調べたわけではないので何とも言えないが、多かれ少なかれ似たようなことは行われている。もし近い将来、プラチナNISAが正式に認められ、毎月分配型投資信託がNISAの対象になった時は、こういう特性があるのだという点に留意して利用して欲しい。

鈴木雅光(すずき・まさみつ)
金融ジャーナリスト
JOYnt代表。岡三証券、公社債新聞社、金融データシステムを経て独立し(有)JOYnt設立し代表に。雑誌への寄稿、単行本執筆のほか、投資信託、経済マーケットを中心に幅広くプロデュース業を展開。
> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!