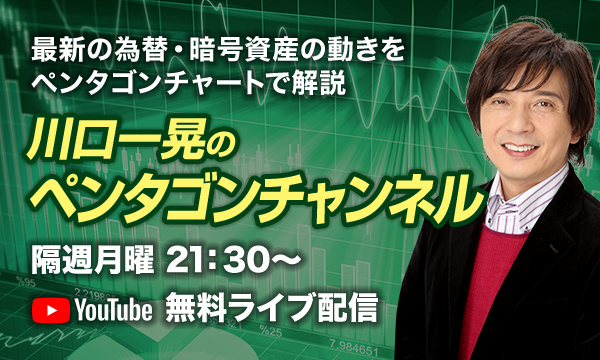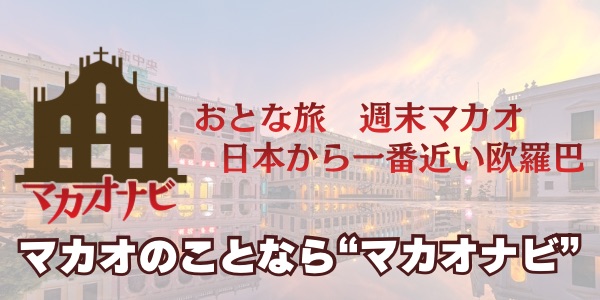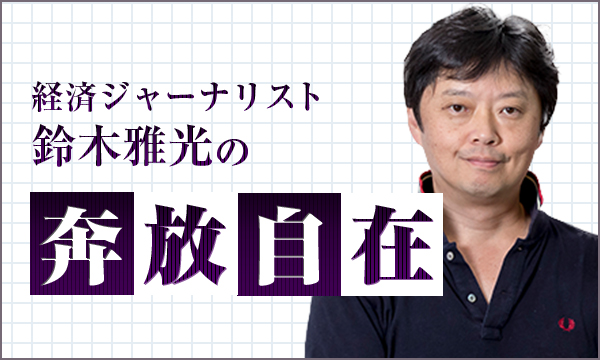長期金利が1.7%に
> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!

日本の長期金利が17年ぶりに1.7%台へ。金融政策の正常化が進む一方で、住宅ローンや社債、国債利回りなど私たちの暮らしへの影響も広がりつつあります。そのポイントをわかりやすく解説します。
日本の長期金利は10月10日、1.7%まで上昇しました。この水準は2008年7月以来、実に17年ぶりの水準です。2019年6月には、▲0.29%というマイナス金利の時もありましたが、この6年で国内長期金利も、ようやく正常化に向けた動きを見せています。
とはいえ、政策金利はまだ0.5%で底這いの状況が続いています。前回、政策金利が見直されたのは2025年1月24日に開かれた金融政策決定会合でのこと。この時は0.25%だった無担保コール翌日物の誘導目標を0.5%に引き上げました。
そして直近に開かれた金融政策決定会合は9月18・19日でしたが、この時は政策金利の見直しは行われず、無担保コール翌日物の誘導目標を0.5%で維持することとなりました。
ただし、日本銀行が保有しているETFおよびJ-REITについて、長い時間をかけて市場売却を進めることを発表しました。これは金融政策の正常化の一環と捉えられますが、マーケットへの影響は限定的です。そもそも売却額からして、現在、日銀が保有しているETFとJ-REITを全部売却するには100年以上かかりますし、売却額を途中で引き上げるにしても、よほどマーケットが堅調に推移しない限りは実施しないと思われます。


また、日銀が保有しているETFやJ-REITを市場に売却するということは、株式市場やJ-REIT市場から資金を吸い上げる効果があるため、見方を変えれば、金融引締めの一環であると考えられなくもありませんが、あくまでも株式市場とJ-REIT市場からの資金吸収になるので、金利への影響はほぼゼロでしょう。そもそも前述したように、100年以上かけて行われる市場売却ですから、その影響は軽微であると考えられます。
では、私たちの生活面で、長期金利の上昇はどのような影響を及ぼすでしょうか。
長期金利とは、具体的には10年物国債の利回りを指します。利回りとは、債券市場で10年物国債が売買されることによって形成されます。
そして、この10年物国債の利回りが上昇すると、新しく発行される国債の利率が引き上げられます。その結果、たとえば個人向け国債や、企業が長期資金を調達するために発行する社債の利率にも影響を及ぼします。
長期金利上昇による影響は、債券市場だけではなく、銀行が企業向けに融資を行う際の融資金利にも及びます。長期金利が上昇すると、長期プライムレートといって、銀行が優良企業向けに長期の融資を行う際の融資金利を引き上げるのです。また長期プライムレートが上昇すれば、優遇金利が適用されない企業に融資を行う際の金利の引き上げにもつながります。
融資金利については、企業向けだけではありません。個人が銀行から住宅ローンを借り入れる際の金利にも影響が及びます。住宅ローン金利には変動金利型と固定金利型がありますが、長期金利の上昇が影響するのは、このうち固定金利型の住宅ローンです。

固定金利型住宅ローンは、たとえば完済までの期間が30年だとすると、完済するまで適用される金利が変わりません。その点では今後、長期金利が1.7%どころか、3%、5%まで上昇したとしても、返済する金額は同じです。
ただし、これはあくまでもすでに借り入れている人の話であって、これから申し込む人にとっては、長期金利の上昇が固定金利型住宅ローンの金利引き上げにつながるため、長期金利が上がれば上がるほど、長期金利が上昇する前に住宅ローンを組んだ人に比べて、月々の返済金額は増えることになります。
ちなみに変動金利型住宅ローンは、定期的に適用金利を見直していくため、金利水準が上昇するほど返済金額は増えることになりますが、変動金利型住宅ローンの適用金利は、長期金利に連動するのではなく、政策金利に連動します。政策金利とは無担保コール翌日物の誘導目標金利を指しています。前述したように、日銀は2025年1月に、政策金利を0.25%から0.5%へと引き上げました。この時点で変動金利型住宅ローンの適用利率も見直されることになりましたが、現状は0.5%から引き上げられる動きがないので、変動金利型住宅ローンの適用金利は現状維持が続いています。
一方、長期金利の上昇は運用面にも影響を及ぼします。たとえば10年物の変動金利型個人向け国債の適用金利は、長期金利が上昇すると見直されることになるため、利子が増えていきます。それと同じく、銀行預金の利率も、たとえば満期までの期間が10年など長期のものについては、長期金利の上昇にともなって適用金利が引き上げられるため、変動金利型個人向け国債と同様、利子が増えていきます。
ただし、固定金利型の長期国債については、長期金利が上昇するほど債券価格が値下がりしていきますので、それを組み入れて運用している債券ファンドは、評価損が基準価額に反映されるため、運用成績は低下していきます。 恐らく、長期金利はこの先も上昇するでしょう。その前提に立てば、今のうちに何が有利で、何が不利なのかを頭の片隅に入れておくことが肝心です。

鈴木雅光(すずき・まさみつ)
金融ジャーナリスト
JOYnt代表。岡三証券、公社債新聞社、金融データシステムを経て独立し(有)JOYnt設立し代表に。雑誌への寄稿、単行本執筆のほか、投資信託、経済マーケットを中心に幅広くプロデュース業を展開。

> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!