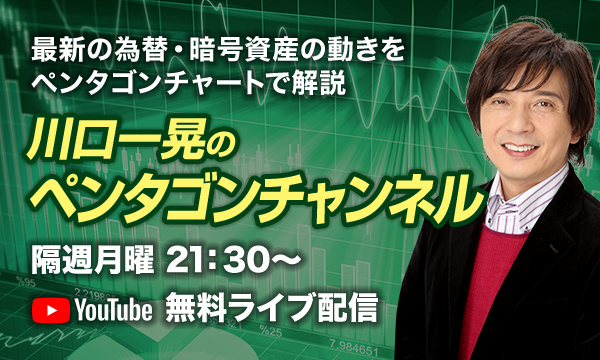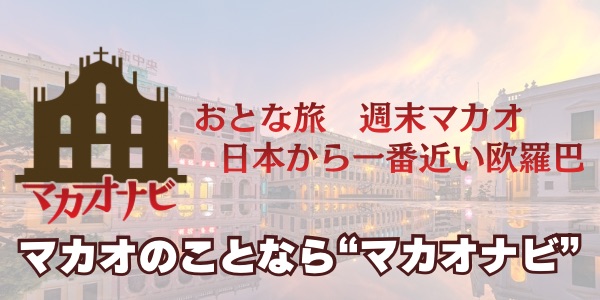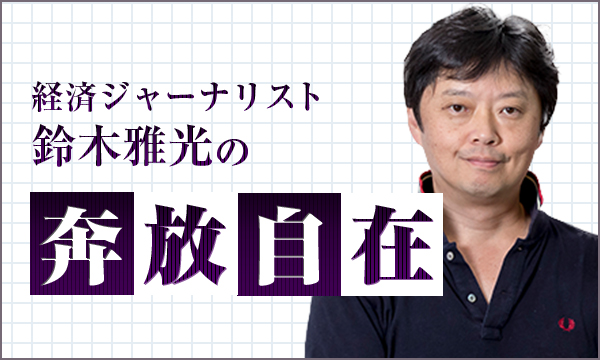金利正常化への道
> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!

デフレ脱却とインフレ加速の中、日本の金利は徐々に正常化の道をたどっています。長期金利の上昇と海外投資家の動きから見える“次の一手”とは?
日本の長期金利に該当する10年物国債の利回りは、2022年12月あたりから本格的な上昇トレンドに入りました。
新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されていた2021年当時の長期金利は0.01%水準で推移していましたが、2022年からは0.25%前後で、2023年に入ってから6月前後までは0.5%を上限に推移するようになり、同年7月からは多少の上下はあるものの、一気に上昇トレンドに移行していきました。
そして2025年5月半ばには、1.57%をつけるところまで水準を切り上げてきています。

長期金利が上昇しているのは、日本の金利が徐々に正常化へと向かっている証とも言えるでしょう。
日本銀行は2024年3月に異次元金融緩和を終え、同年8月から月間の国債買入額を四半期ごとに4000億円ずつ減らしてきました。結果、減額開始前は月5.7兆円だった買入額が、2026年3月までに、月間2.9兆円になる予定です。
日本銀行は2013年から異次元金融緩和を行ってきました。黒田前日銀総裁の時代です。「アベノミクス」、「黒田バズーカ」のセットで、デフレ脱却を目指しました。
しかし、日本の悪性デフレは極めてしつこく、政府・日銀がインフレ目標値としていた消費者物価指数の2%上昇は、なかなか実現しませんでした。結局、コアCPIと言われる「生鮮食品を除く総合」の数字でそれが実現したのは、2022年4月以降のことです。それ以降、コアCPIはさらに上昇を続け、2025年5月時点のそれは3.7%にもなりました。これはいささかオーバースピードといえるでしょう。2025年4月時点の米国の消費者物価指数上昇率は2.3%、ユーロ圏が2.2%、英国が3.5%ですから、目下、日本のインフレ率が先進国中、最も高いと言えます。
30年以上にもわたってデフレが続いた日本の消費者物価が、ここに来て他の先進国よりも上昇しているのはなぜでしょうか。
恐らく物価上昇を抑えるのに十分なほどまでに、金利が上昇していないからではないでしょうか。
前述したように、長期金利の指標となる10年国債利回りは、6月時点で1.4%台。政策金利である無担保コール翌日物金利は0.48%です。
たとえば米国の消費者物価指数は、2021年3月から本格的な上昇に転じ、それまでは1~2%台で推移していたのが、2022年6月には9.1%まで上昇しました。2022年中を通じて7~9%台で推移した後、徐々に物価は落ち着き始め。2025年4月には2.3%まで低下してきたのです。
そして、この間の金利を見ると、米国の長期金利である10年国債の利回りは、2022年に入ってから上昇局面に入り、同年10月には4%を突破。2023年10月には5%に達しました。また、短期金利の指標となるFFレートも、2022年2月の0.25%から3月には0.5%、5月に1%、6月に1.75%、7月に2.5%というように、矢継ぎ早に誘導目標が引き上げられ、2023年7月には5.5%まで上昇しました。ここまで思い切って利上げを行い、ようやく消費者物価指数の上昇率が落ち着いてきたのです。
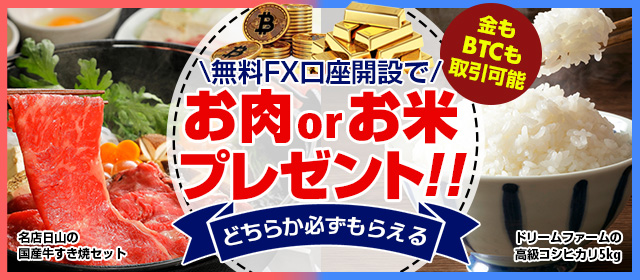

対して日本の場合、ここまで積極的な利上げが行えない状況です。理由はいくつか考えられます。
第一に、景気がまだ盤石といえるほどにしっかりしていないと見られていることです。
そして第二に、これが非常に大きいのではないかと思われるのは、日本の財政が非常に悪いことです。
それを証拠に、日本国債の格付は、かなり厳しい状況にあります。それぞれの日本国債の格付がどうなっているのかというと、表のようになります。
日本国債の格付け
| 格付け機関 | ランク |
|---|---|
| S&P | A+ |
| ムーディーズ | A1 |
| フィッチ | A |
| R&I | AA+ |
| JCR | AAA |
では、どれを見るのが正しいのか、ということですが、日本国債の格付を見るうえで大事なのは、海外投資家がどう考えるかということです。なぜなら、日本国債についても徐々に海外投資家の保有比率が高まってきているからです。
日本の財政赤字については、「さらに国債の発行が増えたとしても、基本的に日本国内でファイナンスできるから安心」と言われますが、これは日本国債を保有している投資家が、基本的に日本の預金取扱機関、保険会社、年金基金、公的年金が中心だった時代の話です。
2010年3月末の国債保有の構成比を見ると、海外投資家の保有比率は5.54%であり、残りはすべて日本国内の預金取扱機関、保険会社、年金基金、公的年金などによって保有されていました。だから、財政出動が増えて国債をたくさん発行することになったとしても、必ず買い手がいるからファイナンスできる、と言われてきましたが、今やその状況は大きく変わっています。「国庫短期証券」と「国債・財投債」を合わせた海外投資家の保有比率が、2010年3月末の5.54%から、2024年12月末には11.89%まで上昇しているのです。
海外投資家は海外の格付を中心にウォッチしているので、その格付が下がれば、日本国債への投資を控える恐れがあります。つまり、日本国債のファイナンスに支障を来すリスクが生じてきます。こうした背景から、日本の金利がなかなか上がらない状況にあると考えられます。

鈴木雅光(すずき・まさみつ)
金融ジャーナリスト
JOYnt代表。岡三証券、公社債新聞社、金融データシステムを経て独立し(有)JOYnt設立し代表に。雑誌への寄稿、単行本執筆のほか、投資信託、経済マーケットを中心に幅広くプロデュース業を展開。
> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!